ラジオ番組出演のお知らせ(3月16日) [息抜き!?]
久しぶりに、ラジオ出演します!
ラジオ関西「ばんばひろふみ ラジオDEショー!」
今回は私の冠番組ではなく、兵庫県弁護士会の活動の一環です。
3月16日am11:09〜番組中の『知の玉手箱』のコーナーでにゲストで。
働き方を変えてLOVE &PEACEの世界を作ろう、という話をしたいと思っています。
「ご笑聴」いただければ幸いです!
リアルタイムでなくても、アプリradicoでは1週間聴いていただくことができます。
https://jocr.jp/banban/?fbclid=IwAR2ruG0V_8tcVSW1ExO7xzwl4PtXMDIaMy1FM4IVH-PNC1jwcxRA4cNjQ3E
ラジオ関西「ばんばひろふみ ラジオDEショー!」
今回は私の冠番組ではなく、兵庫県弁護士会の活動の一環です。
3月16日am11:09〜番組中の『知の玉手箱』のコーナーでにゲストで。
働き方を変えてLOVE &PEACEの世界を作ろう、という話をしたいと思っています。
「ご笑聴」いただければ幸いです!
リアルタイムでなくても、アプリradicoでは1週間聴いていただくことができます。
https://jocr.jp/banban/?fbclid=IwAR2ruG0V_8tcVSW1ExO7xzwl4PtXMDIaMy1FM4IVH-PNC1jwcxRA4cNjQ3E
映画「ああ栄冠は君に輝く」 [息抜き!?]
http://www.eikanhakimini.com/

映画公式 http://www.eikanhakimini.com
いよいよ,夏の高校野球,甲子園始まりました。
今年は第100回記念大会,初日から超満員です。
最近,アメトークの影響もあってか,甲子園の観客の入りが凄いですね。
私も大会初日,第三試合 慶應義塾vs中越の試合を観に行きました。
今年担当した司法修習生が慶應義塾高校の出身だった関係で,一緒に慶應アルプスに入れてもらいました。私も慶應関係者になりきって,慶應ボーイたちと肩を組んで応援しました。
試合は9回劇的なサヨナラ勝ちで,湧き上がるアルプスの中,野球観戦というか応援を堪能させてもらいました。
さてさて,続いて,本日は映画を観てきました。
これも縁あって知り合った方が製作に関わられた作品で,夏の甲子園の大会歌「栄冠は君に輝く」の歌詞を作った人の物語です。
「栄冠は君に輝く」の作詞は「加賀道子」とされているのですが,本当の作詞者はその夫の「加賀大介」であり,その「加賀大介」さんの物語です。
加賀大介さんは,野球が大好きな少年でした。
いつも裸足で野球をしていたのですが,あるとき足に傷を負ったのをそのまま処置しないでいたところ化膿して骨髄炎にまで悪化し,片脚の膝下を切断せざるをえなくなり,野球ができなくなってしまいます。
その後,加賀大介さんは文筆家になるのですが,昭和23年に朝日新聞社が夏の全国高校野球選手権大会の大会歌の歌詞を募集したところに応募します。
自身は野球ができないのですが,野球をしていたときの感覚,夢中で野球をする少年たちの姿などから一気に書き上げ,「栄冠は君に輝く」が誕生します。
理由(これは,興味ある方は本,映画などで)あって妻「加賀道子」名で提出したところ,見事,大会歌に選出されてしまったというお話です。
さて,ここからは私自身の話。
やっぱり少年時代は「野球」ほど魅力的なものはありませんでした。
昭和生まれの男子,山に囲まれた篠山で,やっぱり男の子の遊びはまず野球。
「習い事」とか正式のチームの野球と違って,水田に囲まれた運動場で,なんとか人数を集めて(それでも9人などはめったに集まりません)やる野球。
ファールフライを打ち上げてボールがフェンスを超えたら,水田にポチャリ。
みんなで裸足で水田をぬぷぬぷ歩いて(たまにカエルも踏んづけてしまいます),やっとボールを拾ってゲーム再開。
篠山の小学生だったときの友達の姿が懐かしく思い出されます。
灘高に入学した後,私も念願の「高校球児」になりました。
でも,甲子園に届かないどころか,余りに野球が下手だったのと,当時は色々興味が移って(「ロックバンドでもやった方がモテるかな」などと思って),一年生のときにやめてしまいました。
だから,甲子園でみる野球部員のまぶしさは,私には特にまぶしく見えます。
でも大人になっても「野球好き」はどうしても残っていて,弁護士になってから,神戸の弁護士会野球チーム「神戸ドルフィンズ」で今は毎週草野球をする生活です。
相変わらず下手ですが,いつかは好打・好守の「名内野手」になる,というのが趣味の世界の目標です。
「栄冠は君に輝く」の歌詞は,片脚を切断し野球をプレーすることが叶わなくなった加賀大介さんが書いた詩。
それだけに,「栄冠は君に輝く」は何も甲子園に出場できる球児だけに向けられた詩ではない。
あらゆる人に「栄冠は輝く」というメッセージなんだそうです。
もちろん,甲子園球児にも。
甲子園に届かなかった球児にも。
高校球児ではないけれども野球好きの人(私のような草野球のおっさん)にも。
野球が好きだけれども,実際にはプレーできない人にも。
それを取り巻く全ての人にも。
昨日もテレビの特別番組でやっていましたが,甲子園といえば,松坂大輔や松井秀喜らのスーパースター,池田高校・PL学園・大阪桐蔭などの滅茶苦茶強い学校,こういう「圧倒的なもの」を観る楽しみも,もの凄い魅力です。
ですが,一方で,甲子園に出ないけれども4000校を超える学校の野球部があって,それぞれの野球部員,マネージャーにそれぞれの物語があって,また,高校時代に部活や自分の活動に思い切り打ち込めた人もいればそうでない人もいる。
それは高校生だけでなく大人になってもみんなそう。
でもそれぞれに「物語」があるし,「栄冠」がある,という,加賀大介さんの,あらゆる人への想像力あふれる思いの詩だった,と知ったとき,涙が出るほど感動しました。
メジャーな映画でないので,どこで観られるかは公式HPで要チェックです。
普段よく目につく映画(「君の名は」みたいなメジャーなもの)以外にも,貴重な映画の世界があるのだなあ,と思います。
文化・芸術は目立つものだけでなく,生き続ける中に「宝物」を含むものだなあ,と感じました。

ああ栄冠は君に輝く~加賀大介物語~ 知られざる「全国高校野球大会歌」誕生秘話
- 作者: 手束 仁
- 出版社/メーカー: 双葉社
- 発売日: 2015/07/18
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
映画公式 http://www.eikanhakimini.com
いよいよ,夏の高校野球,甲子園始まりました。
今年は第100回記念大会,初日から超満員です。
最近,アメトークの影響もあってか,甲子園の観客の入りが凄いですね。
私も大会初日,第三試合 慶應義塾vs中越の試合を観に行きました。
今年担当した司法修習生が慶應義塾高校の出身だった関係で,一緒に慶應アルプスに入れてもらいました。私も慶應関係者になりきって,慶應ボーイたちと肩を組んで応援しました。
試合は9回劇的なサヨナラ勝ちで,湧き上がるアルプスの中,野球観戦というか応援を堪能させてもらいました。
さてさて,続いて,本日は映画を観てきました。
これも縁あって知り合った方が製作に関わられた作品で,夏の甲子園の大会歌「栄冠は君に輝く」の歌詞を作った人の物語です。
「栄冠は君に輝く」の作詞は「加賀道子」とされているのですが,本当の作詞者はその夫の「加賀大介」であり,その「加賀大介」さんの物語です。
加賀大介さんは,野球が大好きな少年でした。
いつも裸足で野球をしていたのですが,あるとき足に傷を負ったのをそのまま処置しないでいたところ化膿して骨髄炎にまで悪化し,片脚の膝下を切断せざるをえなくなり,野球ができなくなってしまいます。
その後,加賀大介さんは文筆家になるのですが,昭和23年に朝日新聞社が夏の全国高校野球選手権大会の大会歌の歌詞を募集したところに応募します。
自身は野球ができないのですが,野球をしていたときの感覚,夢中で野球をする少年たちの姿などから一気に書き上げ,「栄冠は君に輝く」が誕生します。
理由(これは,興味ある方は本,映画などで)あって妻「加賀道子」名で提出したところ,見事,大会歌に選出されてしまったというお話です。
さて,ここからは私自身の話。
やっぱり少年時代は「野球」ほど魅力的なものはありませんでした。
昭和生まれの男子,山に囲まれた篠山で,やっぱり男の子の遊びはまず野球。
「習い事」とか正式のチームの野球と違って,水田に囲まれた運動場で,なんとか人数を集めて(それでも9人などはめったに集まりません)やる野球。
ファールフライを打ち上げてボールがフェンスを超えたら,水田にポチャリ。
みんなで裸足で水田をぬぷぬぷ歩いて(たまにカエルも踏んづけてしまいます),やっとボールを拾ってゲーム再開。
篠山の小学生だったときの友達の姿が懐かしく思い出されます。
灘高に入学した後,私も念願の「高校球児」になりました。
でも,甲子園に届かないどころか,余りに野球が下手だったのと,当時は色々興味が移って(「ロックバンドでもやった方がモテるかな」などと思って),一年生のときにやめてしまいました。
だから,甲子園でみる野球部員のまぶしさは,私には特にまぶしく見えます。
でも大人になっても「野球好き」はどうしても残っていて,弁護士になってから,神戸の弁護士会野球チーム「神戸ドルフィンズ」で今は毎週草野球をする生活です。
相変わらず下手ですが,いつかは好打・好守の「名内野手」になる,というのが趣味の世界の目標です。
「栄冠は君に輝く」の歌詞は,片脚を切断し野球をプレーすることが叶わなくなった加賀大介さんが書いた詩。
それだけに,「栄冠は君に輝く」は何も甲子園に出場できる球児だけに向けられた詩ではない。
あらゆる人に「栄冠は輝く」というメッセージなんだそうです。
もちろん,甲子園球児にも。
甲子園に届かなかった球児にも。
高校球児ではないけれども野球好きの人(私のような草野球のおっさん)にも。
野球が好きだけれども,実際にはプレーできない人にも。
それを取り巻く全ての人にも。
昨日もテレビの特別番組でやっていましたが,甲子園といえば,松坂大輔や松井秀喜らのスーパースター,池田高校・PL学園・大阪桐蔭などの滅茶苦茶強い学校,こういう「圧倒的なもの」を観る楽しみも,もの凄い魅力です。
ですが,一方で,甲子園に出ないけれども4000校を超える学校の野球部があって,それぞれの野球部員,マネージャーにそれぞれの物語があって,また,高校時代に部活や自分の活動に思い切り打ち込めた人もいればそうでない人もいる。
それは高校生だけでなく大人になってもみんなそう。
でもそれぞれに「物語」があるし,「栄冠」がある,という,加賀大介さんの,あらゆる人への想像力あふれる思いの詩だった,と知ったとき,涙が出るほど感動しました。
メジャーな映画でないので,どこで観られるかは公式HPで要チェックです。
普段よく目につく映画(「君の名は」みたいなメジャーなもの)以外にも,貴重な映画の世界があるのだなあ,と思います。
文化・芸術は目立つものだけでなく,生き続ける中に「宝物」を含むものだなあ,と感じました。
映画『君の名は。』観てきました。 [息抜き!?]
遅ればせながら、観てきました。
まだこれからという人もいると思うので、ネタバレにつながることは書きません。
アニメの進化もすごいな!という感想です。
実写よりも子ども向け、ということは全くありません。
実写と全く違うジャンルの完成度の高い作品という他ありません。
無理矢理「弁護士」に繋げると、
アニメも進化している!
まけずに弁護士も、私も進化しなくては!
というところです。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
映画「ガリレオ 真夏の方程式」を観てきました [息抜き!?]
見終わって、なんだか夏休みが終わってしまったような気分です(早っ!)。
少年が、一夏の思い出、たまたま「博士」(ガリレオ、福山雅治)に出会い、知的好奇心に目覚める得難い経験をする(けど、それだけではない)。
内容は、ネタバレになるといけないので余り書きませんが、なかなか心温まる部分もあり、実に面白い映画でした。
あと、モデルの杏さん演じる女性の生き様というのも味があり、また、市民運動とガリレオという絡みもあり…(もっと書きたい、が、書けない。)
さて、少年と博士の出会いに話を戻すと、子どもの知識や技能を育てること、それはもちろん大切ですが、やっぱり、そのエネルギーの源である「内なるワクワク」を大切にすることがより根本だな、と感じたのでした。
村上英樹(弁護士、神戸シーサイド法律事務所)
銀河英雄伝説 [息抜き!?]
今年、タカラヅカ歌劇の演目で、「銀河英雄伝説」がありそれを観に行ったのがきっかけで、アニメの銀河英雄伝説DVDをTSUTAYAで借りて少しずつ観ています。(今夜も、できれば、銀河の歴史を1ページめくりたい、と思っています。)
アニメは1988年~リリースされたもののようで、主題歌などに、時代を感じさせるものがあるのですが、内容は見応えがあります。
原作は小説。
宇宙戦争をテーマにしたものなのですが、一方の勢力、自由惑星同盟側の主人公ヤン・ウエンリーを通して、作者の思いが色々語られます。
例えば、
独裁者は出現させる側により多くの責任がある。積極的に支持しなくても、黙って見ていれば同罪だ。
という台詞が出てきます。
ですが、独裁に対置する「民主主義」についても、単純に「民主主義」万歳!!と言えない状況に陥りがちだ、という視点も出てきます。
現に、体面上は民主主義にのっとっているかのような体裁は整えるが、実は、権益を守ろうとするだけの自由惑星同盟国防委員長ヨブ・トリューニヒトなどという人物がおり、自由と民主主義を体現する勢力である「自由作成同盟」の民主主義は腐りきっている、というのがアニメの時代背景。
一方の側、「銀河帝国」は、その名の通り、帝政であるが、若きリーダーであるラインハルトが事実上の独裁体制を敷くと、これが案外、それまで社会を牛耳っていた貴族の既得権益等を一掃し、とりあえずは、公正と正義をある程度実現し、市民も歓迎する状態を招く。
自由惑星同盟の名将といわれるヤン・ウエンリーは本当は戦争など大嫌いなのだが、行きがかり上軍人という立場に縛り付けられ続けている。
そんな中、民主主義の担い手のはずの自由惑星同盟政府から、理不尽な要求ばかりを突きつけられ、また、政府が市民のためと思えないことばかりすることから、
「こんなことならいっそ良い独裁なら、独裁のほうが…」「おっと、いかんいかん、今俺は危険なことを考えていた」みたいな自問自答をしたり、独り言を言ったりする。
このヤンの「つぶやき」が、おそらく色んな時代、社会を超えて、何度も顔を出すだろう問いを含んでいるので、なかなか深みのある作品として鑑賞できる。
戦争作品ですが、反戦色は強く、ヤンの台詞に、
「軍隊は道具にすぎない。それも、ないほうがいい道具だ。そのことをおぼえていて、その上でなるべく無害な道具になれるといいね」
というものがあります。また、ヤンは、
軍隊は暴力装置だ
といい(これ自体は、マックス・ウエーバーが言っていることの引用でしょうが)、この暴力の向かう先が民衆であった例が歴史上多いことへの警戒を説きます。
また、国家の都合よりも個人の尊重が先にある、というヤンの考え方は何度も吐露されます。
今の世の中、「民主主義」が一見どうしようもない事態に至っているように見えるけど、でもだからといって、「一気にズバッと解決してくれそうな」安易な対処法に頼るのは危険が一杯だよ、大きな犠牲を払わなければ後戻りできないかもしれないよ。
ちょっとずつでも民主主義を機能するように、地味に見えても、地道にやっていくのが本当の道ではないか。(とはいえ、これも上手くいかないのが現実なのだが、これこそが「よりましな」方法ではないか。)
という作者のメッセージが聴こえる感じの作品です。
そうだね、その通りだ。
でも、 「独裁」を防ぐためには、 「民主主義」を守れ! と叫んだりしているだけではきっとダメなんだろう。
例えば、現に、人々の暮らしが良くならなければ。
そして、一見、民主主義の仕組の中で守られている「不正義」はちゃんと正さなければ。
「独裁者」であっても何でも、正してくれるなら、という期待は分かるもの。そういう期待を私さえ抱きそうになるときがある。
けど、正すプロセスがおかしければ、やっぱりその歪みがある。後々おかしなことになるのだろう。
世の中を変えるにも、守るべき節度の中で、行う必要があるんだろうな。
しかし、それには粘り強さが必要。
この「粘り強さ」が今本当に必要。私自身そんなに「粘り強い」自信はない。「粘り強く」ありたい、と思っているけど。
多くの人とその意識が共有できたらいいのだろう…
というのが、私の感想でした。
村上英樹(弁護士、神戸シーサイド法律事務所)
私の小6時の読書感想文~三国志編 [息抜き!?]
読書感想文の記事を書いたので、続きに、昔、私が小学校6年の時、(たぶん後にも先にも1回だけ)読書感想文で賞をもらったときのことを思い出したので、書いてみます。
読んだのは「三国志」。
何巻もになっているのは読めないので、子ども向けに1巻だけで簡単にダイジェストにしてくれているやつを読んで読書感想文を書きました。
実は、去年帰省したときに、私が使っていた部屋の片隅から、偶然、表彰状と作文そのものを発見しました。
なんと、たいそうに表彰状を額縁にいれて飾っていたのです。
読んでみると…
内容1 三国志の戦はスケールがでかい!日本の戦国時代などよりも、人数も、移動距離も、なにもかも!
→ (大人の私の感想)
いいところを書いていると思うけれども、これ 「あとがき」をぱくったんじゃないか?(たしかそうだった気がする。)
内容2 「死せる孔明、生ける仲達を走らす」のエピソード、死してなお自分の人形を作らせ敵に一泡吹かせた孔明の徹底した策士ぶりに感動!死んだ後のことをそこまで考えるなんて!
→ (大人の私の感想)
いいね、いいねえ。あまりに有名なエピソードだが、誰も一度はここで感動するよね!
この調子!
内容3 蔡瑁(さいぼう)のように、人を裏切る奴はいかん!「関羽のように、人を裏切らず、初心を貫く人こそ立派だと思います。」(終了) (註 蔡瑁は、私が読んだ本では、主君を裏切り曹操に味方したとんでもない奴という風に書かれていた。)
→ (大人の私の感想)
あらら。
最後の一文が「関羽のように、人を裏切らず、初心を貫く人こそ立派だと思います。」で原稿用紙規定枚数ぴったり終了。最後の「○」が左隅にぴったり収まっている。
せっかく内容2までがんばっていたのに、最後の最後がこれでいいの?
って、まあ、きっと当時は、そんなことより、「原稿用紙規定枚数ぴったりだ、やったー」と思っていたんやろうな-。
というものでした。
読んでみると、文章(文法とか原稿用紙の使い方、言い回しなど)は、われながら、小6にしては「がんばっている」と思いました。
内容も2まで、今見てもいい感じに思えます。
が、最後の最後が「人を裏切らない関羽は立派です。」で終わるという、なんというか、悪くはないと思うけど単純というか、まあ、小学生だからこれで良し良し、という感じのものでしょうが、やっぱ何か「惜しい!!」、ま、よく入賞したもんだなあ、と思いました。
それも、子どもらしく真っ直ぐな印象を与えて、それはそれで良かったたということだったのでしょうか。
生意気に「賢ぶって」みたりもしているけど、最後「やっぱ子ども」が露呈している、小6の私の作文。
小6生の、その「(大人になりつつある部分と子どもの部分など)色々」が混ざって現れた作文に、それが面白いから賞をあげよう、ともらえた賞だったのかも。
shiraさんのコメントしてくださった「成長物語」ですが、私の場合、整った「成長した」アピールの形でなくて、「成長しようとがんばっているけれども、まだまだ」な自分の姿をさらけだす形で「成長物語」を体現してしまっていたようです。ラッキーだったのは、きっと、それを好意的に見てくれた大人のがいたということなのでしょう。
そんな感じで、成長の跡(?)を振り返ると、なかなか笑えるようなことも多いものですね。
神戸シーサイド法律事務所
弁護士 村上英樹
読んだのは「三国志」。
何巻もになっているのは読めないので、子ども向けに1巻だけで簡単にダイジェストにしてくれているやつを読んで読書感想文を書きました。
実は、去年帰省したときに、私が使っていた部屋の片隅から、偶然、表彰状と作文そのものを発見しました。
なんと、たいそうに表彰状を額縁にいれて飾っていたのです。
読んでみると…
内容1 三国志の戦はスケールがでかい!日本の戦国時代などよりも、人数も、移動距離も、なにもかも!
→ (大人の私の感想)
いいところを書いていると思うけれども、これ 「あとがき」をぱくったんじゃないか?(たしかそうだった気がする。)
内容2 「死せる孔明、生ける仲達を走らす」のエピソード、死してなお自分の人形を作らせ敵に一泡吹かせた孔明の徹底した策士ぶりに感動!死んだ後のことをそこまで考えるなんて!
→ (大人の私の感想)
いいね、いいねえ。あまりに有名なエピソードだが、誰も一度はここで感動するよね!
この調子!
内容3 蔡瑁(さいぼう)のように、人を裏切る奴はいかん!「関羽のように、人を裏切らず、初心を貫く人こそ立派だと思います。」(終了) (註 蔡瑁は、私が読んだ本では、主君を裏切り曹操に味方したとんでもない奴という風に書かれていた。)
→ (大人の私の感想)
あらら。
最後の一文が「関羽のように、人を裏切らず、初心を貫く人こそ立派だと思います。」で原稿用紙規定枚数ぴったり終了。最後の「○」が左隅にぴったり収まっている。
せっかく内容2までがんばっていたのに、最後の最後がこれでいいの?
って、まあ、きっと当時は、そんなことより、「原稿用紙規定枚数ぴったりだ、やったー」と思っていたんやろうな-。
というものでした。
読んでみると、文章(文法とか原稿用紙の使い方、言い回しなど)は、われながら、小6にしては「がんばっている」と思いました。
内容も2まで、今見てもいい感じに思えます。
が、最後の最後が「人を裏切らない関羽は立派です。」で終わるという、なんというか、悪くはないと思うけど単純というか、まあ、小学生だからこれで良し良し、という感じのものでしょうが、やっぱ何か「惜しい!!」、ま、よく入賞したもんだなあ、と思いました。
それも、子どもらしく真っ直ぐな印象を与えて、それはそれで良かったたということだったのでしょうか。
生意気に「賢ぶって」みたりもしているけど、最後「やっぱ子ども」が露呈している、小6の私の作文。
小6生の、その「(大人になりつつある部分と子どもの部分など)色々」が混ざって現れた作文に、それが面白いから賞をあげよう、ともらえた賞だったのかも。
shiraさんのコメントしてくださった「成長物語」ですが、私の場合、整った「成長した」アピールの形でなくて、「成長しようとがんばっているけれども、まだまだ」な自分の姿をさらけだす形で「成長物語」を体現してしまっていたようです。ラッキーだったのは、きっと、それを好意的に見てくれた大人のがいたということなのでしょう。
そんな感じで、成長の跡(?)を振り返ると、なかなか笑えるようなことも多いものですね。
神戸シーサイド法律事務所
弁護士 村上英樹
リセット [息抜き!?]
先週は、夏休みを頂いていました。
その関係で連絡等が遅くなった方には、お詫び申し上げます。
ただ、御陰で、自分の仕事の質を向上させるためには、たまには何日間かでも頭を空っぽにすることは、大変役に立つと実感しました。
休みの間、普段出来ない経験や普段会わない人たちと会って、これから、自分が仕事にどう向き合うか、何をやるか、そんなことも考えることが出来ました。
目先の忙しさへの対応と、長いスパンでの仕事の質の向上というのは、時に衝突しますが、バランスをよく考えるべき問題ですね。
今年後半もどうぞよろしくお願いします。
村上英樹(弁護士、神戸シーサイド法律事務所)
その関係で連絡等が遅くなった方には、お詫び申し上げます。
ただ、御陰で、自分の仕事の質を向上させるためには、たまには何日間かでも頭を空っぽにすることは、大変役に立つと実感しました。
休みの間、普段出来ない経験や普段会わない人たちと会って、これから、自分が仕事にどう向き合うか、何をやるか、そんなことも考えることが出来ました。
目先の忙しさへの対応と、長いスパンでの仕事の質の向上というのは、時に衝突しますが、バランスをよく考えるべき問題ですね。
今年後半もどうぞよろしくお願いします。
村上英樹(弁護士、神戸シーサイド法律事務所)
テルマエ・ロマエで人権を語る!? [息抜き!?]
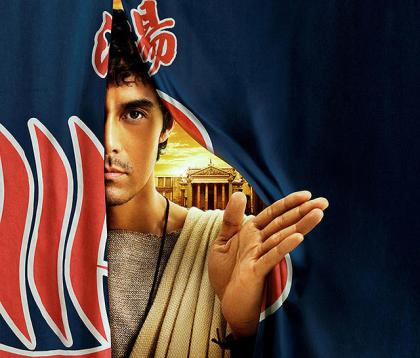
観たかった映画、観てきました。
もう、阿部寛が主人公というだけでも想像してつい笑けてくる、というくらい楽しみにしていました。
実は原作マンガは読んだことがないのですが、映画、実に面白かったです。
きっと原作マンガはさらに(?)素晴らしいに違いない、と思います。
灘校文化祭 今年も [息抜き!?]
GWが近づいて、私のブログ記事でアクセスしていただいている記事の順位が大きく変動しました。
普段は、
養育費・婚姻費用の算定表~なぜ表で決めるのか?
http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14
などの法律知識系の記事にアクセスしていただくことが多かったのですが、GWが近づいてから、
灘校文化祭
http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2011-05-06
のアクセスが急増しました。
我が出身校ながら、恐るべし灘校、と思います。
灘校文化祭は、私が生徒だった約20年前も今も変わらず、5月2日、3日という日程でやっているようです(今年は間違いなくこの日程)。
見学は全くの自由で、今年までのところ、チケット等も何も必要ありません。
ただ、去年(平成23年)行ったときは混んでいました。私の想像を超えて。小学生の親子連れが多かったと思います。
私は、灘校は、高校から入学しているので、文化祭の経験は3回だけ。
高校2,3年のときは、バンドのライブをやりました。BOØWY(ボウイ)などのコピーをやりました(懐かし~)。
生徒の時は、ほとんど自分のことしかやっていませんでしたので、他の催しや展示などはほとんど見ていません。
なので、去年「お客」として行ってみて初めて、
地歴研究会の「砂金掘り」
化学研究会のマジックショー
これも化学?のスライム作り
などのコーナーが小学生に人気があるとか、その他にも、色んな部(特に文化部)の展示が非常に充実していることを知ったのでした。
しかし、お昼ご飯がすぐに売り切れてしまい、コンビニで食糧をゲットしなければならないのは大変でした。
今年行かれる方は、お昼ご飯は自分で用意されることをお勧めします。
今年の灘校は、工事中でちょっと狭い、という話です。
私も、今年も、灘校文化祭を見に行くことにしています。
去年、自分の育った学校の空気を吸って、元気をもらったので。
灘校生は、きっと今年も頑張っているでしょう。
私の時代、多感な時期の灘校生の中には、「受験秀才」というステレオタイプな見方をされることに抵抗し、
俺(たち)は、「勉強」以外がすごいんやぞ!!
とアピールしようと、過剰なまでに、(大して意味のないことにも)エネルギーを注ぐ生徒が少なからずいました。私も、高校時代、意味の分からんギャグばかりを異常な頻度で連発していたのは、そうやって「抵抗」していた、ということでした。
端から見ると、所詮「受験秀才」が背伸びして頑張っている、だったかもしれませんが。
昔の私のような灘校生の姿が、今も見られるのでしょうか。
それとも、今の灘校生は、私のころよりもっとスマートに、自然に自分を表現する生徒が多くなっているのでしょうか。
でもやっぱ、中高生時代の心理というのは昔も今もそんなに変わらないので、私たちのころのように、「脱・受験秀才!」に向けてエネルギーを注いでいる生徒がたくさんいるんじゃないかなぁ、と想像します。
今のほうが昔よりも、「今日日、灘行って、東大行ったからって、だからどうやねん!?」という見方をされることも多いでしょう、そういうことや、色々な感情ありながらも、それでも、みんな日々、色んな方面に着々と力を伸ばしているのだろう、と想像します。
振り返ると、「ギャップ」と意外性を身につけ同世代の女子の歓心をひこうとした、というのが私の高校時代の戦略でした(上手くいったかどうかは微妙)。この辺は、昔の私よりも今の生徒のほうがナチュラルに物事を運び、成功されているのでは?という気がします(人によりましょうが)。
昔より来場者が多くなっていますが、自由な発想で遠慮無く、新しいことをどんどんやる楽しい文化祭であり続けることを祈っています。
村上英樹(弁護士、神戸シーサイド法律事務所)
普段は、
養育費・婚姻費用の算定表~なぜ表で決めるのか?
http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2009-05-14
などの法律知識系の記事にアクセスしていただくことが多かったのですが、GWが近づいてから、
灘校文化祭
http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2011-05-06
のアクセスが急増しました。
我が出身校ながら、恐るべし灘校、と思います。
灘校文化祭は、私が生徒だった約20年前も今も変わらず、5月2日、3日という日程でやっているようです(今年は間違いなくこの日程)。
見学は全くの自由で、今年までのところ、チケット等も何も必要ありません。
ただ、去年(平成23年)行ったときは混んでいました。私の想像を超えて。小学生の親子連れが多かったと思います。
私は、灘校は、高校から入学しているので、文化祭の経験は3回だけ。
高校2,3年のときは、バンドのライブをやりました。BOØWY(ボウイ)などのコピーをやりました(懐かし~)。
生徒の時は、ほとんど自分のことしかやっていませんでしたので、他の催しや展示などはほとんど見ていません。
なので、去年「お客」として行ってみて初めて、
地歴研究会の「砂金掘り」
化学研究会のマジックショー
これも化学?のスライム作り
などのコーナーが小学生に人気があるとか、その他にも、色んな部(特に文化部)の展示が非常に充実していることを知ったのでした。
しかし、お昼ご飯がすぐに売り切れてしまい、コンビニで食糧をゲットしなければならないのは大変でした。
今年行かれる方は、お昼ご飯は自分で用意されることをお勧めします。
今年の灘校は、工事中でちょっと狭い、という話です。
私も、今年も、灘校文化祭を見に行くことにしています。
去年、自分の育った学校の空気を吸って、元気をもらったので。
灘校生は、きっと今年も頑張っているでしょう。
私の時代、多感な時期の灘校生の中には、「受験秀才」というステレオタイプな見方をされることに抵抗し、
俺(たち)は、「勉強」以外がすごいんやぞ!!
とアピールしようと、過剰なまでに、(大して意味のないことにも)エネルギーを注ぐ生徒が少なからずいました。私も、高校時代、意味の分からんギャグばかりを異常な頻度で連発していたのは、そうやって「抵抗」していた、ということでした。
端から見ると、所詮「受験秀才」が背伸びして頑張っている、だったかもしれませんが。
昔の私のような灘校生の姿が、今も見られるのでしょうか。
それとも、今の灘校生は、私のころよりもっとスマートに、自然に自分を表現する生徒が多くなっているのでしょうか。
でもやっぱ、中高生時代の心理というのは昔も今もそんなに変わらないので、私たちのころのように、「脱・受験秀才!」に向けてエネルギーを注いでいる生徒がたくさんいるんじゃないかなぁ、と想像します。
今のほうが昔よりも、「今日日、灘行って、東大行ったからって、だからどうやねん!?」という見方をされることも多いでしょう、そういうことや、色々な感情ありながらも、それでも、みんな日々、色んな方面に着々と力を伸ばしているのだろう、と想像します。
振り返ると、「ギャップ」と意外性を身につけ同世代の女子の歓心をひこうとした、というのが私の高校時代の戦略でした(上手くいったかどうかは微妙)。この辺は、昔の私よりも今の生徒のほうがナチュラルに物事を運び、成功されているのでは?という気がします(人によりましょうが)。
昔より来場者が多くなっていますが、自由な発想で遠慮無く、新しいことをどんどんやる楽しい文化祭であり続けることを祈っています。
村上英樹(弁護士、神戸シーサイド法律事務所)
基礎英語再び! [息抜き!?]
http://www3.nhk.or.jp/netradio/
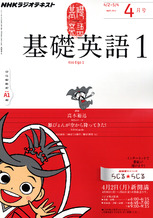
4月1日から、24年ぶり??くらいに基礎英語を聴いています。
高い月謝を払って英語教室に行く前に、英語勉強するなら、まず、コレでしょう!と私は思います。
テキスト代だけで、教授料はタダ。とにかく安い!
おまけに早起きできるきっかけにもなる!
私の作った格言
「基礎英語録音すべからず」
というのがありまして、基礎英語やラジオ英会話を録音して後で聴いて勉強しよう、という案とか、テープ付(現在はCD付)テキストを買って勉強しよう、という案については、私としては成功した試しがなく、結局、
毎日決まった時間に聴く
寝坊して遅刻したらあきらめて、次の日からまた続ける
のが一番上手くいく、と考えています。
現在の「基礎英語1」は、私が中1のときに聴いた「基礎英語」「続基礎英語」とは、少し構成が異なります。
例えば、
This is a pen.
といった感じで、かっちり文法から入っていくのが昔の「基礎英語」だったと記憶していますが、今年の基礎英語は、
4/1はとりあえず「Nice to meet you!」が言えるようにしよう、出来たら、自分の名前と、好きなものもいえたらいうことなし、
といった目標設定で、毎日進んでいく感じです。
その中で、文法が少しずつちりばめられ、きっと最終的に、「基礎英語1」では中1相当くらい(?)の文法が網羅される、というカリキュラムだと思われます。
いわゆる「文法中心」英語で育った世代の私は、昔の「基礎英語」のスタイルのほうが馴染みやすいのですが、別に自分の育った環境がベストとは限りませんよね。
英語圏に出て行くことが昔よりも多くの人にとって現実的なことになった今、こういうスタイルがよい、と考えた「基礎英語」スタッフの発想は、きっと時代に適っているのでしょう。
とはいえ、会話や実践中心の本文でメインが構成されながら、ある程度、予想されるリスナーの語学力の発達具合に応じて文法も適時に巧くフォローしてゆく、というのは、相当な工夫の要ることだと思います。
でも!
私には、近年のNHK教育(Eテレ)などの創意工夫にかける努力は相当なものがあるように見えるので(中には成功していると思われるものも、失敗かな?と思われるものもあるけれど)、今年の「基礎英語」には大いに期待しています。
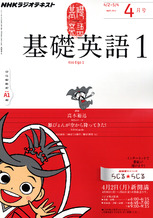
4月1日から、24年ぶり??くらいに基礎英語を聴いています。
高い月謝を払って英語教室に行く前に、英語勉強するなら、まず、コレでしょう!と私は思います。
テキスト代だけで、教授料はタダ。とにかく安い!
おまけに早起きできるきっかけにもなる!
私の作った格言
「基礎英語録音すべからず」
というのがありまして、基礎英語やラジオ英会話を録音して後で聴いて勉強しよう、という案とか、テープ付(現在はCD付)テキストを買って勉強しよう、という案については、私としては成功した試しがなく、結局、
毎日決まった時間に聴く
寝坊して遅刻したらあきらめて、次の日からまた続ける
のが一番上手くいく、と考えています。
現在の「基礎英語1」は、私が中1のときに聴いた「基礎英語」「続基礎英語」とは、少し構成が異なります。
例えば、
This is a pen.
といった感じで、かっちり文法から入っていくのが昔の「基礎英語」だったと記憶していますが、今年の基礎英語は、
4/1はとりあえず「Nice to meet you!」が言えるようにしよう、出来たら、自分の名前と、好きなものもいえたらいうことなし、
といった目標設定で、毎日進んでいく感じです。
その中で、文法が少しずつちりばめられ、きっと最終的に、「基礎英語1」では中1相当くらい(?)の文法が網羅される、というカリキュラムだと思われます。
いわゆる「文法中心」英語で育った世代の私は、昔の「基礎英語」のスタイルのほうが馴染みやすいのですが、別に自分の育った環境がベストとは限りませんよね。
英語圏に出て行くことが昔よりも多くの人にとって現実的なことになった今、こういうスタイルがよい、と考えた「基礎英語」スタッフの発想は、きっと時代に適っているのでしょう。
とはいえ、会話や実践中心の本文でメインが構成されながら、ある程度、予想されるリスナーの語学力の発達具合に応じて文法も適時に巧くフォローしてゆく、というのは、相当な工夫の要ることだと思います。
でも!
私には、近年のNHK教育(Eテレ)などの創意工夫にかける努力は相当なものがあるように見えるので(中には成功していると思われるものも、失敗かな?と思われるものもあるけれど)、今年の「基礎英語」には大いに期待しています。


![銀河英雄伝説 Vol.1 [DVD] 銀河英雄伝説 Vol.1 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41XF23CW0EL._SL160_.jpg)



